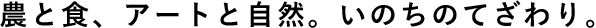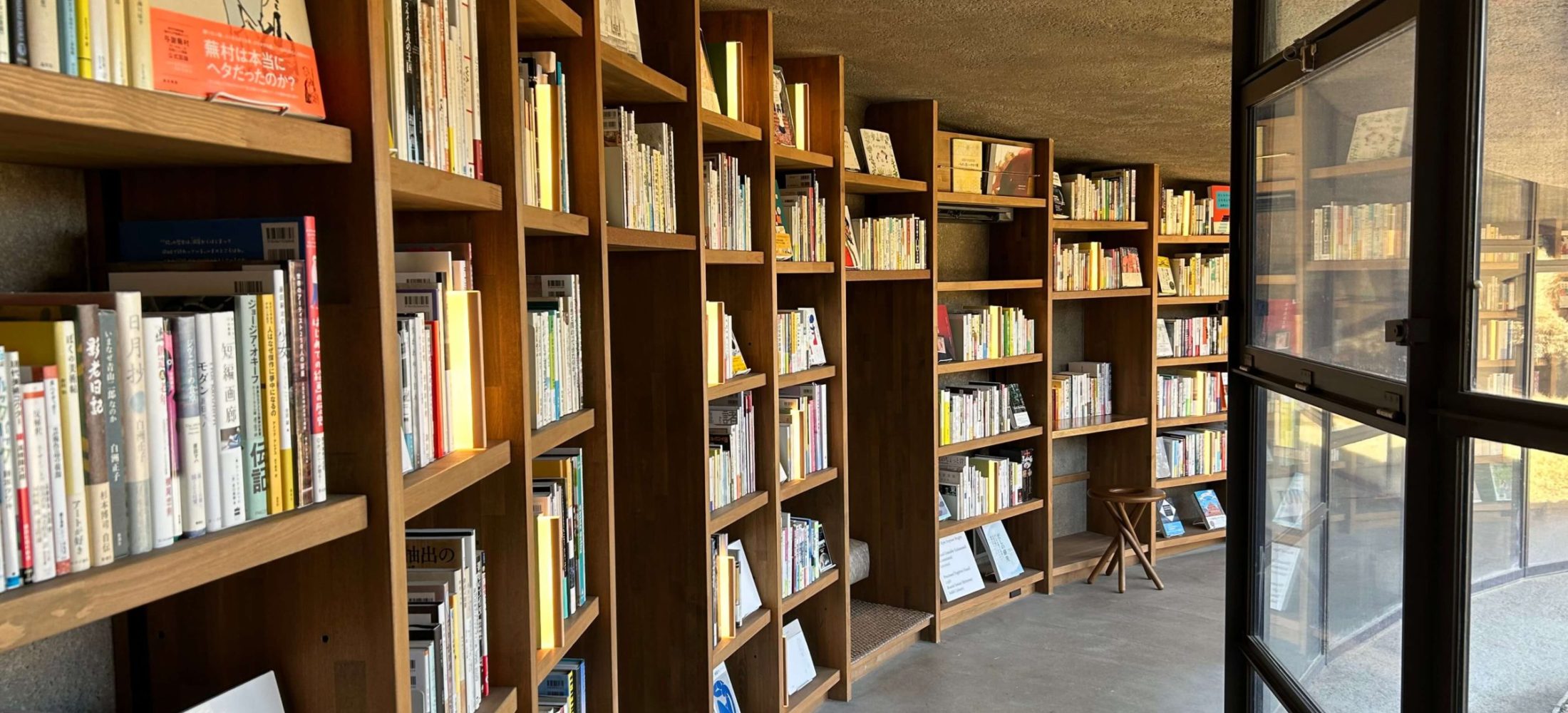VOL.2 冬から始まるカブトムシの観察
UPDATE 2023.1.31
みんなに親しまれている夏の昆虫「カブトムシ」。
クルックフィールズでも夏になるとたくさんの昆虫が森や原っぱで観察できますが、カブトムシはあまり見かけません。ライバルのクワガタムシはよく見かけるのにカブトムシはいない。なぜでしょう?
森を観察しながらその理由を考えていると、少しずつ理由が分かってきました。
まず、カブトムシやクワガタムシの成虫のご飯として必要なコナラやクヌギの森は場内にもあります。成虫が暮らすには問題なさそう。
では幼虫はどうでしょうか?
クワガタムシの幼虫が生息するのは、倒木や朽木の中。場内にも倒木はたくさんあるので、クワガタムシの幼虫が棲んでいそうです。

それに対してカブトムシの幼虫は、落ち葉が溜まってできた腐葉土の中で暮らします。しかし、クルックフィールズの土は粘土質で、腐葉土はほとんどありません。クルックフィールズの森にカブトムシがいない理由はここにあるかもしれません。
この仮説を確かめるために、落ち葉や堆肥を使ってカブトムシの幼虫が安心して暮らせる『カブトムシベッド』と呼ばれる仕掛けを2021年に作ってみました。

作り方はシンプルで、木板や枝を使って枠を作り、そこに落ち葉や堆肥をたくさん入れるだけ。
これだけでカブトムシはやってくるのでしょうか?
結果は一目瞭然。
カブトムシベッドを作ってから約1年。ベッドの土を少し掘ると、カブトムシの幼虫が出るわ、出るわ。
100匹を超える数のカブトムシの幼虫が暮らしているようです。

この冬はお客さまと一緒に新しいカブトムシベッドを作ったので、夏を超えた頃には同じようにたくさんのカブトムシの幼虫が来て、クルックフィールズで成長する姿を見せてくれるかもしれません。
このように、私たちが自然のことを考えて少し工夫するだけで、生き物たちはたちまち反応してくれます。クルックフィールズでは、人も自然の一部と捉えながら、人の存在が地球環境に悪影響を与えるのではなく、私たちがそこに暮らすことでより環境をよくする仕組みが作れないか、日々試行錯誤しています。
カブトムシベッドのように、時にはお客様も一緒になって仕組みを作るワークショップを開催することもありますので、ぜひ参加してみてください。来るたびに、自然を観察する楽しみが増えていきますよ!


1993年千葉県生まれ。大学院で野生生物(対象はアライグマ)の研究をしたのち、ベンチャー企業やリクルートでの営業経験を経て2020年10月に KURKKU FIELDS に入社。「自然の魅力や価値を伝える」ことを人生のミッションとし、KURKKU FIELDSでは循環の仕組みづくりや自然環境保全、果樹づくりを行いながら、来場者向けの体験企画を担当している。