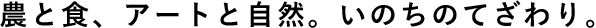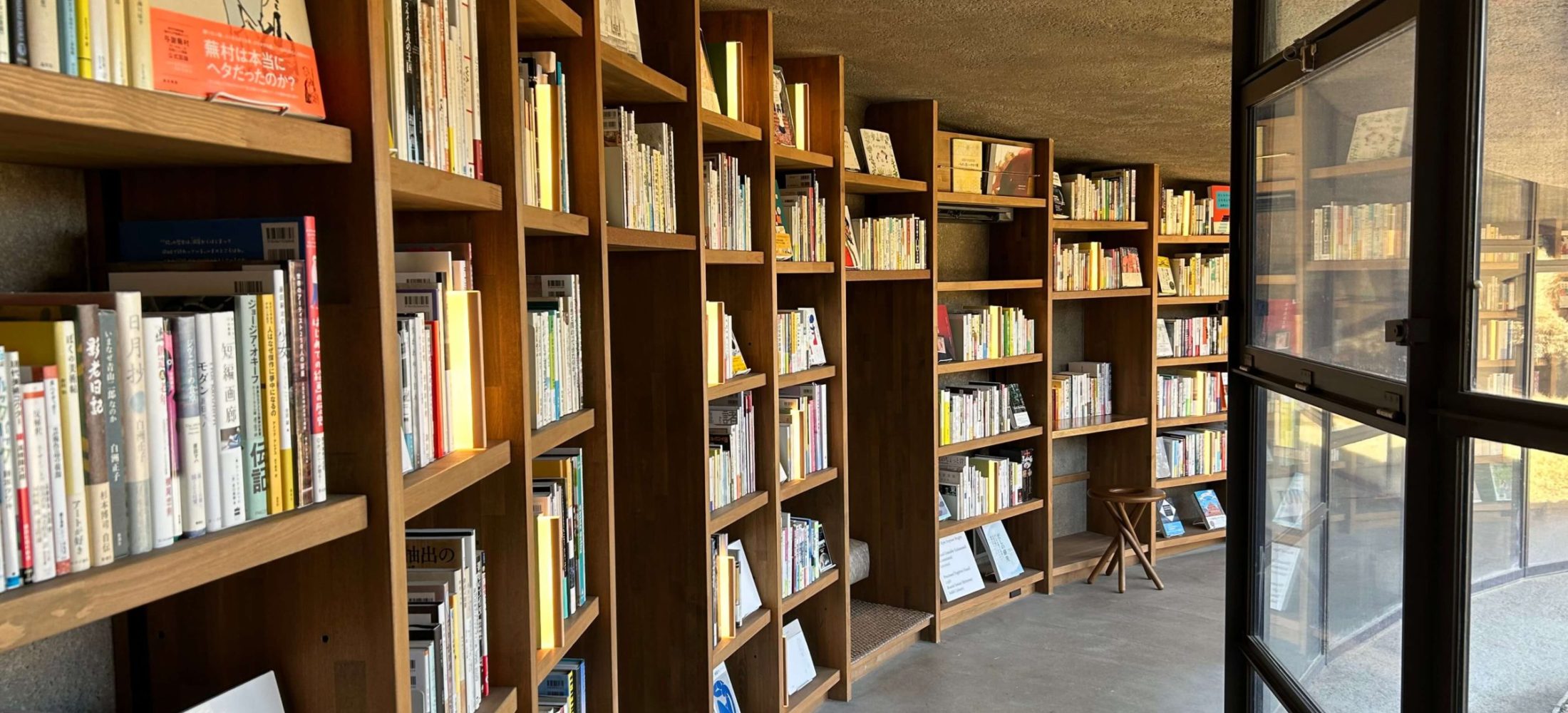VOL.04 カエルのはなし
UPDATE 2023.4.28
こんにちは!クルックフィールズでは、循環の仕組みづくり担当の吉田和哉(よっしー)です!
農場は暖かい日も増え、場内は気持ちのいい新緑に包まれてきました。新緑が目に映え、花々が香り、耳を澄ますと⋯カエルたちの鳴き声が聞こえます!しかしひとくちに『カエル』と言っても、その種類は様々。
今回はカエルの季節に入り、日夜大興奮のわたくしが、魅力的なカエルの世界についてお届けします!
そもそもカエルとは、両生類に分類される脊椎動物。生きていくためには水域と陸域が必要で、クルックフィールズで頻繁に見かけるカエルは5種類前後。クルックフィールズにはどんなカエルが生息するか、活動が活発になる順番でご紹介します!

【 1年に2度も眠る ⁉︎ ヤマアカガエル 】
冬になるとカエルは冬眠をしますが、1年で最も早く目覚めるのはヤマアカガエル。なんと1年間で最も寒い1月末頃には活動を開始し、3月初旬頃までに産卵を行います。
とても戦略的な進化を遂げたカエルで、天敵になるヘビやヤゴが冬眠している間に卵を産むことで、生き残る確率を上げていると考えられています。そしてなんと、繁殖期が終わると、餌が豊富になる5月頃までもう一度眠りに入る「春眠」をします。効率的に自然界を生き抜く素晴らしい進化を遂げているカエルなのです。

【 大きな身体と物憂げな瞳 アズマヒキガエル】
3月に入ると夜でも気温が12℃を越え、雨が降る日が出てきます。するとどうでしょう。示し合わせたように、たくさんのアズマヒキガエル(以下、ヒキガエル)がため池に集まってきました。
集まったヒキガエルたちの多くはオスで、大きな身体を使って相撲を取るようにお互いの強さを見せつけます。その名も「蛙合戦(かわずがっせん)」。
大きな身体は迫力があり、少し怖いかもしれませんが、よく顔を見てください。なんともつぶらな瞳で、少し物憂げな表情をしているヒキガエルは、性格も大人しく落ち着きのある紳士淑女のようなカエルです。


【日本の春の風物詩 ニホンアマガエル、シュレーゲルアオガエル】
ヒキガエルとほぼ同時期に姿を現すのはニホンアマガエルとシュレーゲルアオガエル。
ヒキガエルの繁殖期はたった1週間ほどしかありませんが、この2種類のカエルは3月中旬から4月にかけて連日大合唱をしています。この時期にクルックフィールズに泊まったことがある方は、その大合唱に驚いた方もいると思います(鳴き声が大きすぎて、眠れなかった方はすみません⋯)。
「クワックワックワッ」と鳴くのはニホンアマガエル。
「ケロロロロッ、ケロロロロッ」と鳴くのはシュレーゲルアオガエル。
聞き分けが難しいですが、シュレーゲルアオガエルの鳴き声はもののけ姫に出てくるこだまというキャラクターの出す音色にそっくり!
「こだまのような鳴き声が聞こえたらシュレーゲルアオガエル」と覚えておけば間違いありません。

【 木登りの天才 モリアオガエル 】
農場で最後に繁殖をするのはモリアオガエル。
4月の下旬、夜間の気温が15℃を超えた雨の日に、5cmを超える大きな緑色の美しいカエルが道路を渡っている姿を見かけます。それがモリアオガエルです!
他のカエルは、冬眠時期を除くと1年を通してしばしば見かけますが、モリアオガエルは1年のうち4月下旬から5月にかけて、繁殖期にしか見かけることができません。
それもそのはず、モリアオガエルは樹上性で、1年のうち多くの時間を木の上で過ごしているのです。樹上生活に適応するためか、長い手足の先には大きな吸盤があり、高いジャンプ力を誇ります。なんとも面白いのはその繁殖方法。卵(卵塊)だって樹の上で産んでしまうのです!
この時期になると、モリアオガエルのお母さんは樹木の枝にわたあめのような泡の塊を産みつけ、その中に卵が隠れています。興味深いのはわたあめ状の卵の真下には必ず池があり、雨が降ると、雨と一緒にポツポツとオタマジャクシが水面に落ちていきます。森林を使ったなんともダイナミックで、痛快な繁殖方法。
毎年モリアオガエルの卵を見つけると感動せずにはいられません。
以上、カエルの魅力のほんの一部をご紹介させていただきました。
中間捕食者であるカエルは、農業に悪影響を与える虫たちを食べてくれる私たちの大切なパートナーですが、その多くが生息環境の減少により、個体数を減らしています。
カエルを通して考える自然環境と私たちの暮らし。適度な陸域と水域が必要な生き物だからこそ、その姿をもって私たちに身近な自然の面白さと儚さを教えてくれるのです。

1993年千葉県生まれ。大学院で野生生物(対象はアライグマ)の研究をしたのち、ベンチャー企業やリクルートでの営業経験を経て2020年10月に KURKKU FIELDS に入社。「自然の魅力や価値を伝える」ことを人生のミッションとし、KURKKU FIELDSでは循環の仕組みづくりや自然環境保全、果樹づくりを行いながら、来場者向けの体験企画を担当している。